かかりつけの病院が、サニメドを取り扱っているかご確認ください。
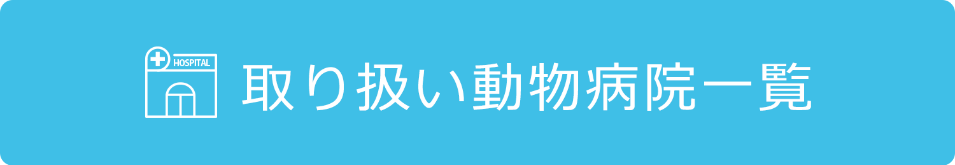
現在位置:

尿石症は猫がかかりやすい病気の一つですが、原因について詳しく知らない方も多いでしょう。猫の尿石症には、食生活や生活習慣、猫自身の体質などが深く関わっています。
本記事では、猫の尿石症の原因や症状、治療法や予防法について解説します。愛猫の尿石症を予防したい・対策方法が知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。


 尿石症の猫には、トイレの回数が増える、トイレでじっとしている、尿に血が混じっている、尿の量が少ないなどの様子がみられます。猫によっては、トイレ以外の場所で粗相をしてしまったり、排尿時に痛みを感じて鳴いたりすることもあるでしょう。
尿石症の猫には、トイレの回数が増える、トイレでじっとしている、尿に血が混じっている、尿の量が少ないなどの様子がみられます。猫によっては、トイレ以外の場所で粗相をしてしまったり、排尿時に痛みを感じて鳴いたりすることもあるでしょう。
また、感染を伴う場合は発熱や食欲不振、元気消失などの症状が現れます。さらに、尿に混じって排出された結石が猫砂やトイレシートの上でキラキラ光って見えることもあります。
なお、尿石症の症状で最も注意が必要なのは、結石が尿路に詰まる「尿道閉塞」です。尿がまったく出せなくなると、膀胱破裂や急性腎不全、尿毒症を起こす可能性があり非常に危険です。特にオス猫は尿道閉塞のリスクが高いため、注意しなければなりません。
 猫の尿石症はさまざまな要因によって発症します。
猫の尿石症はさまざまな要因によって発症します。
ここでは、猫の尿石症を引き起こす主な原因を5つに分けて解説します。
 スコティッシュ・フォールドやヒマラヤン、アメリカン・ショートヘアは、シュウ酸カルシウム結石ができやすい猫種といわれています。
スコティッシュ・フォールドやヒマラヤン、アメリカン・ショートヘアは、シュウ酸カルシウム結石ができやすい猫種といわれています。
尿石症は性別に関係なく発症しますが、重症化しやすいのは尿道が狭く結石が詰まりやすいオス猫です。
また、太っている猫は脂肪で尿道が圧迫されるため、結石による尿路閉塞のリスクがより高いといえるでしょう。
 尿石症をそのままにしておくと、尿路内の結石は徐々に増えていきます。
尿石症をそのままにしておくと、尿路内の結石は徐々に増えていきます。
尿路閉塞を起こした場合は猫の命に関わるため、治療はできるだけ早く受けることが大切です。
猫の尿石症の治療方法には、主に以下のようなものがあります。

尿石症を起こす猫は多いため、日頃の予防が肝心です。猫に負担がかからない程度に、できることから始めてみましょう。
ここでは、猫の尿石症を予防する主な方法を解説します。

猫の尿石症は、一度発症すると再発する可能性が高い病気です。愛猫の尿石症リスクを下げるためにも、ぜひ今回紹介した予防法を生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
尿石症に配慮したキャットフードをお探しなら、「猫用アンチストルバイト」を活用ください。
猫用アンチストルバイトは下部尿路の健康維持に配慮し、ミネラル含有量を調整。ナトリウム含有量が控えめなため、一生涯安心して予防・治療にお使いいただけます。オメガ3脂肪酸「DHA・EPA」が豊富なサーモンオイル配合で、お魚の美味しい香りがふわりとするとともに、猫の健康を内側からサポートします。
購入をご希望の場合は、ぜひかかりつけの動物病院までお問い合わせください。
獣医師の先生にご相談ください。
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。