かかりつけの病院が、サニメドを取り扱っているかご確認ください。
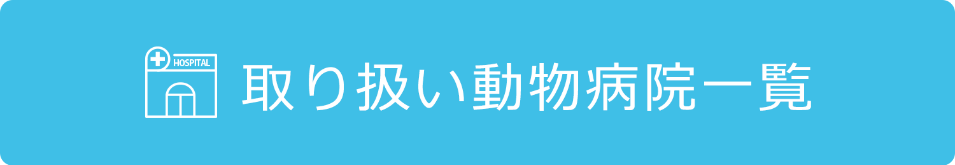
現在位置:

私たち人間に比べて、犬の皮膚はとても薄くデリケートです。
そのぶん豊富な被毛に覆われてはいますが、そのせいで通気性が悪くなり、皮膚トラブルを起こす犬も少なくありません。
愛犬の皮膚を健康に保つためには、なぜ皮膚病になるのか、どんな予防法があるのかを把握しておくことが大切です。
本記事では犬の皮膚病の症状や代表的な病気、治療法や予防法について解説します。愛犬の皮膚に不安がある方はぜひ参考にしてください。


犬の皮膚病の原因は多岐にわたりますが、代表的なものとして以下が挙げられます。
1.細菌・真菌
2.害虫・寄生虫
3.ストレス
4.アレルギー
5.高温多湿・乾燥
犬の皮膚病の原因になりうる要因について次の項目から詳しく解説します。
 犬の皮膚病には多くの種類がありますが、その中で代表的なものとして以下8つをご紹介します。
犬の皮膚病には多くの種類がありますが、その中で代表的なものとして以下8つをご紹介します。
1.膿皮症(ノウヒショウ)
2.アトピー性皮膚炎
3.脂漏症(シロウショウ)
4.マラセチア性皮膚炎
5.皮膚糸状菌症|皮膚糸状菌
6.毛包虫症(モウホウチュウショウ)|ニキビダニ・アカラス
7.疥癬(カイセン)|ヒゼンダニ
8.食物アレルギー
 個体差はありますが、以下の犬種は皮膚病にかかりやすい傾向があります。
個体差はありますが、以下の犬種は皮膚病にかかりやすい傾向があります。
・パグ
・柴犬
・シー・ズー
・キャバリア
・フレンチ・ブルドッグ
・コッカー・スパニエル
・ゴールデン・レトリーバー
・ウエスト・ハイランド・ホワイテリア
生まれつき皮膚が脂っぽい犬種やアレルギー体質の犬種は皮膚病にかかりやすいといえます。
また、パグやフレンチ・ブルドッグなど短頭種の場合、顔のシワに汚れが溜まりやすく、細菌繁殖によって皮膚病を引き起こすケースが多いでしょう。
そのほか、皮膚のバリア機能が未熟な子犬や免疫力が落ちた老犬も皮膚病にかかりやすいため、注意が必要です。
 犬の皮膚病の治療は、原因や症状に合ったものを行います。皮膚病は完治まで時間がかかるものも多く、自宅でのケアも欠かせません。
犬の皮膚病の治療は、原因や症状に合ったものを行います。皮膚病は完治まで時間がかかるものも多く、自宅でのケアも欠かせません。
ここでは、犬の皮膚病の主な治療法を3つに分けて解説します。
 犬の皮膚病を予防するには、適切なスキンケアと環境整備が必要です。
犬の皮膚病を予防するには、適切なスキンケアと環境整備が必要です。
定期的なシャンプーやブラッシングで皮膚を清潔に保ち、愛犬の皮膚バリアを整えてあげましょう。
さらに、虫が活発に活動する時期は必ず予防薬を投与して、愛犬を寄生虫から守ることも大切です。
犬が生活する部屋は常に快適な温度・湿度を維持するようにし、細菌や真菌が繁殖しにくい環境を保ちましょう。
なお、健やかな皮膚を保つためには、栄養バランスの整った食事が欠かせません。
私たち人間と同じく、犬も食べたもので体が作られます。
愛犬の皮膚に不安がある場合は、皮膚によい栄養素を含むドッグフードを与えるとよいでしょう。
 犬の皮膚はとてもデリケートなため、些細なことでトラブルが生じます。
犬の皮膚はとてもデリケートなため、些細なことでトラブルが生じます。
日頃から愛犬の様子をよく観察し、皮膚病の予防や早期発見に努めましょう。
愛犬の皮膚トラブルにお悩みなら、サニメドの「ハイドロライズドプロテイン」をお試しください。
ハイドロライズドプロテインは、食物アレルギーによる皮膚炎や消化器症状を抱える犬たちのために作られた、特別なドッグフードです。
グルテンフリーであり、原料に加水分解タンパク質(フィッシュ)を使用することでアレルギーを起こしにくくし、スムーズな消化吸収を実現。
また、オメガ3脂肪酸を豊富に含むサーモンオイルと亜麻仁油を配合しています。
さらに、オメガ6脂肪酸の中でも皮膚炎への治療効果が期待されているγ-リノレン酸を含むボラージオイルもバランスよく配合しており、皮膚・被毛の健康を内側からサポートします。
給与は獣医師の診断と指導の下で行っていただくため、まずはお気軽に、かかりつけの動物病院で「ハイドロライズドプロテインに興味がある」旨をお伝えください。
獣医師の先生にご相談ください。
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。