かかりつけの病院が、サニメドを取り扱っているかご確認ください。
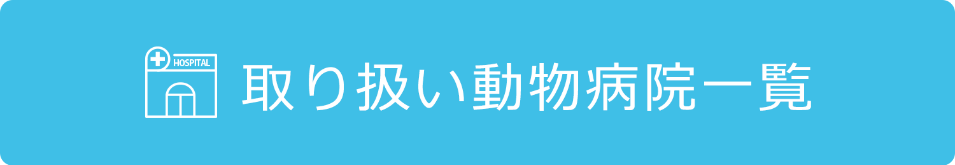
現在位置:

動物病院を受診すると、獣医師から「療法食」が必要と診断されることがあります。療法食は一般的なフードとは異なる特徴を持っており、適切な取り扱いが必要です。
本記事では、犬の療法食についてペットオーナーさんが正しく理解できるよう、犬の療法食の目的や特徴、主な種類や与える際の注意点について解説します。犬が療法食を食べないときの対処法も解説しているため、療法食の食いつきに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
 療法食とは、特定の病気や健康状態に合わせて作られたドッグフードのことです。一般的なドッグフードと違い、療法食は製品ごとに栄養成分の量や比率が特別に調整されています。そのため、継続して与えることで 健康状態の維持や病気の進行を遅らせるサポートが期待できるでしょう。
療法食とは、特定の病気や健康状態に合わせて作られたドッグフードのことです。一般的なドッグフードと違い、療法食は製品ごとに栄養成分の量や比率が特別に調整されています。そのため、継続して与えることで 健康状態の維持や病気の進行を遅らせるサポートが期待できるでしょう。
療法食にはさまざまな種類がありますが、いずれも獣医師の診断・指導に基づいた給与が推奨されています。自己判断で誤った与え方をすると、かえって犬の健康を害する可能性もあるため、扱いには十分に注意しましょう。
 犬の療法食は、製品ごとに対象の病気や特徴が異なります。療法食の有用性を最大限発揮させるためにも、適切な種類の療法食を与えましょう。
犬の療法食は、製品ごとに対象の病気や特徴が異なります。療法食の有用性を最大限発揮させるためにも、適切な種類の療法食を与えましょう。
各療法食の栄養組成はメーカーによって異なりますが、ここでは主な療法食の種類7つとその特徴について解説します。
 療法食は医薬品ではありませんが、獣医師が治療の一環として使用する特別なドッグフードです。そのため、犬に与える際は取り扱いに十分注意しなければなりません。療法食の正しい扱い方を知り、愛犬の治療のサポートや体調管理に役立てましょう。
療法食は医薬品ではありませんが、獣医師が治療の一環として使用する特別なドッグフードです。そのため、犬に与える際は取り扱いに十分注意しなければなりません。療法食の正しい扱い方を知り、愛犬の治療のサポートや体調管理に役立てましょう。
ここでは、犬に療法食を与える際に最低限知っておくべき4つの注意点について解説します。
 いざ愛犬に療法食を与えても、食べてくれなかったり残してしまったりすると困ってしまいますよね。警戒心が強い犬や食にこだわりがある犬では、療法食を拒否することも珍しくありません。
いざ愛犬に療法食を与えても、食べてくれなかったり残してしまったりすると困ってしまいますよね。警戒心が強い犬や食にこだわりがある犬では、療法食を拒否することも珍しくありません。
ここでは、犬が療法食を食べないときの主な対処法を解説します。
 犬の療法食は、病気治療のサポートや再発防止の補助、体型管理などに活用できる、特別なドッグフードです。ただし、栄養成分の量や比率が特別に調整されているぶん、間違った与え方をすると体調を崩す恐れがあるため、必ず獣医師の指導のもと与えましょう。
犬の療法食は、病気治療のサポートや再発防止の補助、体型管理などに活用できる、特別なドッグフードです。ただし、栄養成分の量や比率が特別に調整されているぶん、間違った与え方をすると体調を崩す恐れがあるため、必ず獣医師の指導のもと与えましょう。
犬用の療法食をお探しなら、ぜひSANIMED(サニメド)をご検討ください。
サニメドはヨーロッパを始め、世界中で愛用されている療法食ブランドです。フードはすべて最新の栄養学に基づいてレシピを組んでおり、安全性が高い原材料を使用しています。人工添加物不使用のため、継続的に与える際も安心です。
まずはお気軽に、かかりつけの動物病院にて「サニメドに興味がある」旨をお伝えください。
獣医師の先生にご相談ください。
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
\犬・猫との楽しい暮らしに役立つ情報をお届け/