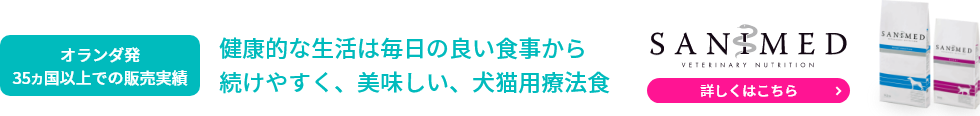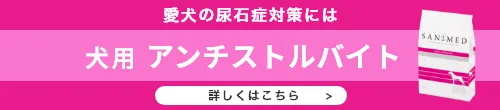犬の混合ワクチンは接種したほうがよい?接種スケジュールや費用などを解説

愛犬の健康を守るために考える必要がでてくることのひとつに「混合ワクチン」をどのように接種するか、ということが挙げられます。このワクチン、実は狂犬病ワクチンのように接種が法律で義務付けられているわけではありませんが、犬同士で感染する可能性のある病気を防ぐために、接種が推奨されています。
今回のコラムでは、混合ワクチンとはなにか?なぜ接種したほうがよいのか?費用は?などといったことについて詳しくご説明しますので、お知りになりたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
犬の混合ワクチンは、どんな病気を防げるの?

まず、混合ワクチンは「コアワクチン」「ノンコアワクチン」に大きく分けられ、該当する感染症は以下になります。伝染力が強いものもあり、感染した場合、特に幼犬で重症化するケースが多いです。
コアワクチン:生活環境に関わらず、すべての犬に接種すべきワクチン
① 犬 パルボウイルス 感染症
激しい嘔吐や下痢、重度の脱水といった症状が見られる感染症です。嘔吐や便を介して感染するため、散歩時に他の犬の便に接触した結果、感染してしまったという例もあります。
② 犬 ジステンパーウイルス 感染症
くしゃみや咳などの呼吸器症状、下痢や嘔吐などの消化症状などが見られる非常に伝播力が強いウイルスです。感染している犬の唾液、尿などへの接触で感染し、時には脳にまで進行し、その場合、けいれんや麻痺などが見られる場合があります。
③ 犬 伝染性肝炎 (アデノウイルスⅠ型 感染症)
嘔吐、下痢などの消化器症状や、重症化すると肝臓の腫大や黄疸などが引き起こされることがあります。感染した犬の唾液や尿への接触で感染します。
③ 犬 伝染性喉頭気管炎 (アデノウイルスⅡ型 感染症)
ペットショップなどで幼犬の間で広がることが多いことでよく知られる「ケンネルコフ」の原因のひとつです。短い乾いた咳や鼻水がみられ、こちらに接触することで感染します。
ノンコアワクチン:地域環境や暮らし方によって接種を検討すべきワクチン
① 犬 パラインフルエンザウイルス 感染症
アデノウイルスⅡ型感染症と同様に「ケンネルコフ」の原因のひとつです。短い乾いた咳や鼻水がみられ、こちらに接触することで感染します。
② 犬 レプトスピラウイルス 感染症
特にげっ歯類が保有する確率が高いとされており、ヒトにも感染する人獣共通感染症です。感染動物の尿に排泄され、接触することで感染します。発熱や食欲不振が見られ重症化すると黄疸、肝不全などが引き起こされることがあります。
③ 犬 コロナウイルス 感染症
嘔吐や下痢といった消化器症状が見られる感染症です。感染した犬の便に接触することで感染します。
日本で販売されているワクチンは種類が多くありますが、動物病院で導入されているケースが多い、5種~10種まで、対応できるウイルスについて、以下の表に記載します。

*犬 レプトスピラウイルスは複数の型あり。
どの種類を接種すればよい?副反応はあるの?

「かかりつけでは6種と8種があるけど、やはり種類が多い方が良いの?」という疑問の声を時折耳にしますが、接種する種類が多ければ多い方が良い、というものではありません。
前述したとおり、コアワクチンはすべての犬に必要なので、必ず接種したいですが、5種以上のワクチンにはこれらはすべて含まれています。
7種以上のワクチンに含まれる「レプトスピラ症」については、ネズミなどのげっ歯類の尿で汚染された水や土壌との接触で感染することが判明しているので、キャンプなどのアウトドアにいくことがあるなど、感染の可能性がある場合は、接種が推奨されます。
一方、都心部で近所の散歩くらいしか外出はしない、という場合は、6種で十分である、という考え方もあります。 (ただ、都心部での感染が認められたケースもありますので、近所でそういった事例がないか、ネズミの出没情報はないか、確認するようにするとよいでしょう。)
動物病院の方針によっても使用しているワクチンの種類は異なりますので、実際に愛犬にどの種類のワクチンを接種すべきか、主治医の先生とご相談ください。
接種をするうえで気になるのが副反応ですが、起こる可能性は高くはないものの、あります。例として接種部位の痒みや痛み、顔や全身が腫れる、元気消失・食欲不振が挙げられます。重篤なものとしてアナフィラキシーショックがありますが、こちらは接種後すぐ(30分以内)に起こることが多いため、しばらく待合室でなにも起きないか、待って確認することをお勧めします。
また、その後、仮になにかあっても対応ができるように、終日受診が可能な日の、午前中に接種するのがベストです。
接種のスケジュールは?費用はどの程度かかる?

スケジュールについて、移行抗体(母体からの免疫)により守られている間は十分な免疫が得られない可能性が考慮され、1回目は生後6週~8週 、その後3週間ずつ間隔をあけて、2回目、3回目接種、その後は1年ごとに追加接種、というのが現在日本では一般的になっています。
ただ、2024年にコアワクチンの接種頻度の国際的な方針が改定されているため、愛犬にとって最適なスケジュールについては、主治医の先生にご相談ください。
費用に関しては動物病院によって異なりますが、1回の接種につき5,000円~10,000円以内におさまるケースがほとんどです。
接種後に「ワクチン証明書」が交付されます。ドッグランやペットホテルを利用する際に提示を求められることも多いので、なくさないようにしましょう。
まとめ

ワクチン接種は、その子が感染症にかからない、かかっても重症化しないことが大きな目的になりますが、地域社会全体での疾患の流行を防ぐ、という目的もあります。感染症の流行阻止には約70%以上の集団免疫が必要とされており、個を守るワクチンが結果集団免疫を果たし、より強力なワクチンの効果を得ることができます。
時には命もおびやかす感染症から大切な愛犬を守るために、主治医の先生と相談しながら、最適なワクチンを接種していくようにしましょう。