かかりつけの病院が、サニメドを取り扱っているかご確認ください。
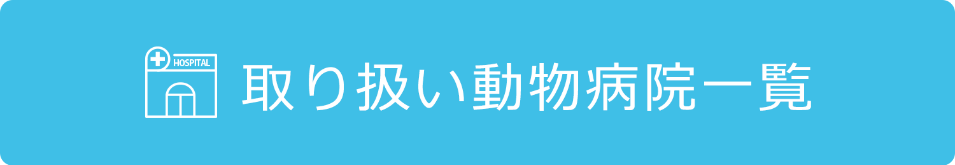
現在位置:

数あるキャットフードのなかでも、「療法食」は特別な特徴を持った食事です。そのため、どんな種類があるのか気になる方も多いでしょう。
本記事では、猫の療法食の目的や主な種類、与える際の注意点や食べないときの対処法を解説します。最後まで目を通せば猫の療法食について正しい知識を得ることができるため、「療法食を適切に使いたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
 特定の病気や健康状態の猫に対して、獣医師が治療の一環とし使用する食事を「療法食」といいます。猫の療法食は栄養成分の量や比率が調整されており、病気の治療や再発防止のサポート、または進行を遅らせる補助としての役割があります。
特定の病気や健康状態の猫に対して、獣医師が治療の一環とし使用する食事を「療法食」といいます。猫の療法食は栄養成分の量や比率が調整されており、病気の治療や再発防止のサポート、または進行を遅らせる補助としての役割があります。
猫の病気のなかには食事管理が必要なものも多くありますが、病気に合った適切な栄養の食事をペットオーナーさんが用意するのは現実的ではありません。療法食は食事管理が必要な猫の主食として与えられるフードであり、猫の健康管理に役立つ特別な食事といえるでしょう。
 ひとくちに療法食といっても、その種類や特徴はさまざまです。それぞれの療法食の特徴をよく理解し、愛猫の病気治療のサポートや健康管理に役立てましょう。
ひとくちに療法食といっても、その種類や特徴はさまざまです。それぞれの療法食の特徴をよく理解し、愛猫の病気治療のサポートや健康管理に役立てましょう。
ここでは、猫の療法食のうち一般的に広く利用されている種類6つ とその特徴について解説します。
 療法食を販売する店舗・ネットショップは複数ありますが、基本的にはかかりつけの動物病院で購入しましょう。療法食はメーカーや製品によって栄養成分の量や比率が違うため、愛猫にぴったり合うものを獣医師に選んでもらう必要があります。獣医師から指示されたものを動物病院で購入すれば、きちんとした栄養指導のもと給餌ができるでしょう。
療法食を販売する店舗・ネットショップは複数ありますが、基本的にはかかりつけの動物病院で購入しましょう。療法食はメーカーや製品によって栄養成分の量や比率が違うため、愛猫にぴったり合うものを獣医師に選んでもらう必要があります。獣医師から指示されたものを動物病院で購入すれば、きちんとした栄養指導のもと給餌ができるでしょう。
また、ネットで購入できる療法食のなかには、並行輸入品が混ざっていることもあります。並行輸入品の療法食は正規品よりリーズナブルに販売されていますが、品質や管理レベルに不安があり、おすすめできません。メーカー本社の認証を受けていないため、健康トラブルなどが起こっても自己責任であることを考えると、購入は避けたほうが良いといえるでしょう。
 初めて猫に療法食を与えるときは、どんなことに気をつけたらよいいか不安を感じる方も多いでしょう。
初めて猫に療法食を与えるときは、どんなことに気をつけたらよいいか不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、愛猫 の食事療法をスムーズに行うため、療法食を与えるうえで事前に知っておきたいことやフードの切り替え方について解説します。
 療法食が必要だと診断されたからといって、この先ずっと続けなければいけないわけではありません。獣医師の判断によりますが、治療が成功し療法食の必要が無くなれば、経過観察のうえ少しずつ一般のフードに切り替えられる場合もあるでしょう。
療法食が必要だと診断されたからといって、この先ずっと続けなければいけないわけではありません。獣医師の判断によりますが、治療が成功し療法食の必要が無くなれば、経過観察のうえ少しずつ一般のフードに切り替えられる場合もあるでしょう。
ただし、猫の体質や病気によっては継続的に与えなくてはいけなかったり、一度落ち着いた症状がぶりかえしたりする可能性もあるため、「もう大丈夫だろう」と自己判断で止めてはいけません。療法食を止めるタイミングは、あくまで獣医師の判断にゆだねるようにしましょう。
 猫が療法食を食べてくれない場合、どうすればいいか悩んでしまいますよね。一般的に療法食はその他のフードより嗜好性が低いため、普段から食へのこだわりが強かったり、食べムラがあったりする猫では、療法食を食べないことも珍しくありません。
猫が療法食を食べてくれない場合、どうすればいいか悩んでしまいますよね。一般的に療法食はその他のフードより嗜好性が低いため、普段から食へのこだわりが強かったり、食べムラがあったりする猫では、療法食を食べないことも珍しくありません。
ここでは、猫が療法食を食べないときに試してほしい対処法を5つ紹介します。
 療法食は正しく活用すれば、高い効果が期待できる特別なキャットフードです。しかし自己判断で給餌を止めたり、市販品を購入して与えたりすると、かえって猫の健康を害する恐れがあるため、取り扱いには注意しましょう。
療法食は正しく活用すれば、高い効果が期待できる特別なキャットフードです。しかし自己判断で給餌を止めたり、市販品を購入して与えたりすると、かえって猫の健康を害する恐れがあるため、取り扱いには注意しましょう。
猫用の療法食をお探しなら、ぜひSANIMED(サニメド)をご検討ください。
サニメドはヨーロッパを始めとした、世界中で愛用されている療法食ブランドです。フードは最新の栄養学に基づいてレシピを組んでおり、安全な原材料を使用。人工添加物を使用していないのも、安心して続けられるポイントです。
サニメドではさまざまな疾患・状態に対応できるよう複数のラインナップを揃えているため、ご検討の際はかかりつけの動物病院にてご相談ください。
獣医師の先生にご相談ください。
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
\犬・猫との楽しい暮らしに役立つ情報をお届け/