かかりつけの病院が、サニメドを取り扱っているかご確認ください。
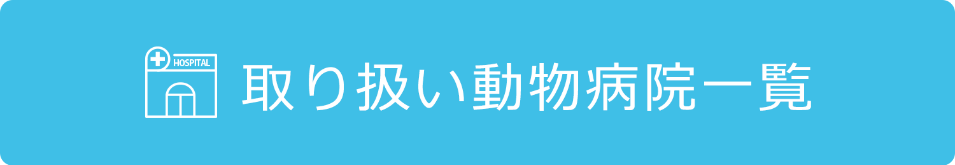
現在位置:

人間の病気と思いがちな糖尿病ですが、実は猫が発症するケースも珍しくありません。本記事では、猫の糖尿病の主な原因や症状、治療法について解説します。
この記事を読むことで猫の糖尿病について詳しく知ることができ、愛猫の異変に気付きやすくなるでしょう。糖尿病を予防する方法も解説しているため、猫の糖尿病が心配という方はぜひ参考にしてください。
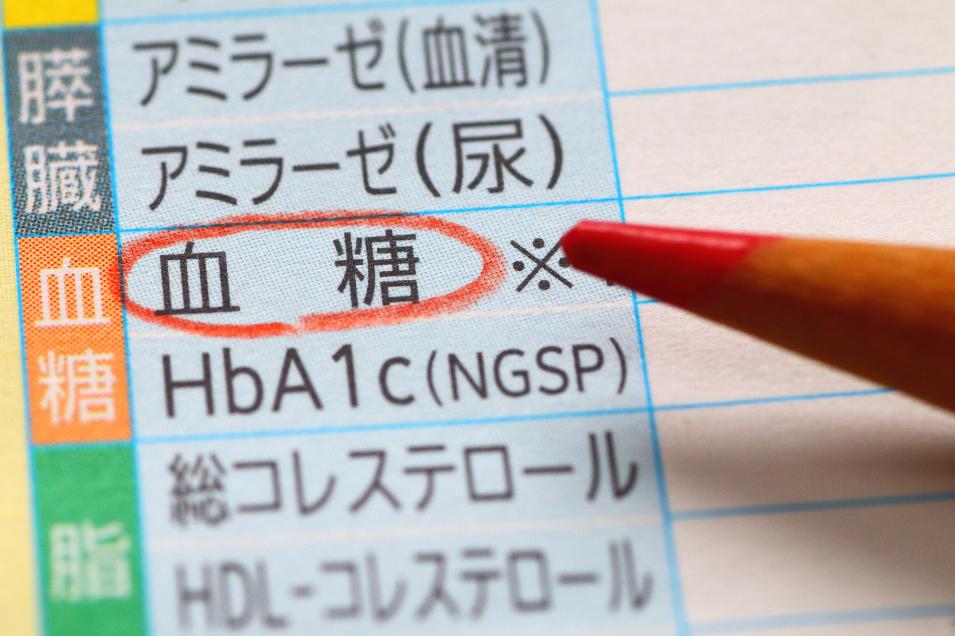 猫の糖尿病は、血液中のブドウ糖である「血糖」が増えすぎてしまう病気です。血液中には常に一定量のブドウ糖が存在しており、膵臓から分泌されるインスリンによって血糖値が調整されています。このインスリンがなんらかの原因で不足したり、作用が弱まったりすることで慢性的な高血糖を起こした状態を糖尿病といいます。
猫の糖尿病は、血液中のブドウ糖である「血糖」が増えすぎてしまう病気です。血液中には常に一定量のブドウ糖が存在しており、膵臓から分泌されるインスリンによって血糖値が調整されています。このインスリンがなんらかの原因で不足したり、作用が弱まったりすることで慢性的な高血糖を起こした状態を糖尿病といいます。
猫の糖尿病には「1型糖尿病」と「2型糖尿病」の2種類がありますが、猫では2型糖尿病の罹患率が高いといわれています。また、犬に比べて猫は糖尿病になりやすい傾向があるため、普段から意識して生活習慣を整えることが大切です。
 猫の糖尿病には、食事やストレスなどの生活習慣が深く関わっています。特に肥満の猫は糖尿病になりやすいため、注意が必要です。糖尿病の主な原因を知って、糖尿病の予防に努めましょう。
猫の糖尿病には、食事やストレスなどの生活習慣が深く関わっています。特に肥満の猫は糖尿病になりやすいため、注意が必要です。糖尿病の主な原因を知って、糖尿病の予防に努めましょう。
ここでは、猫の糖尿病の主な原因を5つに分けて解説します。
 猫の糖尿病は、初期と末期で症状が大きく異なります。糖尿病は適切な治療を行わなければ徐々に進行していくため、早期治療が大切です。
猫の糖尿病は、初期と末期で症状が大きく異なります。糖尿病は適切な治療を行わなければ徐々に進行していくため、早期治療が大切です。
なるべく早く治療につなげられるよう、末期症状はもちろん、初期症状も覚えておきましょう。
 猫の糖尿病は中年期以降で発症しやすいため、10歳前後の猫は特に注意が必要です。なかでも肥満の猫や膵炎の猫、甲状腺機能亢進症などのホルモン疾患を持つ猫は、糖尿病の発症リスクが高い傾向があります。
猫の糖尿病は中年期以降で発症しやすいため、10歳前後の猫は特に注意が必要です。なかでも肥満の猫や膵炎の猫、甲状腺機能亢進症などのホルモン疾患を持つ猫は、糖尿病の発症リスクが高い傾向があります。
糖尿病はステロイドによって起こるケースもあるため、皮膚炎や口内炎などの治療でステロイドを長期使用している場合も、注意が必要といえるでしょう。糖尿病はオスメスどちらも罹患する可能性はありますが、メス猫に比べてオス猫の発症リスクが高いとされています。なお、発症しやすい猫種はないとされています。
 糖尿病の進行を防ぐには、早期発見・早期治療が大切です。猫の糖尿病の治療法には、主に「インスリン投与」と「食餌療法」、「入院治療」の3つがあります。
糖尿病の進行を防ぐには、早期発見・早期治療が大切です。猫の糖尿病の治療法には、主に「インスリン投与」と「食餌療法」、「入院治療」の3つがあります。
ここでは、各治療を行う目的や主な内容について解説します。
 猫の糖尿病の多くは生活習慣が原因で発症するため、普段の生活環境を見直すことが予防につながります。
猫の糖尿病の多くは生活習慣が原因で発症するため、普段の生活環境を見直すことが予防につながります。
ここでは、猫の糖尿病を予防するポイントを解説します。
 猫の糖尿病はさまざまな原因で発症する病気であり、基本的に一生涯のインスリン投与が必要です。治療はかかりつけの獣医師とよく相談しながら、より良い方法を見つけていくと良いでしょう。
猫の糖尿病はさまざまな原因で発症する病気であり、基本的に一生涯のインスリン投与が必要です。治療はかかりつけの獣医師とよく相談しながら、より良い方法を見つけていくと良いでしょう。
糖尿病の猫の食事をお探しなら、サニメドの「猫用ウェイトリダクション」がおすすめです。
「猫用ウェイトリダクション」は食後血糖値の動きに配慮し、食物繊維・タンパク質を高配合するとともに、脂質と炭水化物配合量を低めに設定しています。 摂取エネルギーは制限しつつ、必要なタンパク質・ビタミン・ミネラルが確保されているため、健康的な減量をはじめ、糖尿病の猫の普段の食事としても最適です。
サニメドは動物病院専売品のため、興味がある方はかかりつけの動物病院で「サニメドを試したい」とお伝えください。
獣医師の先生にご相談ください。
※サニメドは特定の疾病または健康状態にある犬猫の療法食です。一般的な維持食とは異なるため、必ずかかりつけの獣医師の診断と指導の下で給与を開始していただくことをお願いしております。
\犬・猫との楽しい暮らしに役立つ情報をお届け/