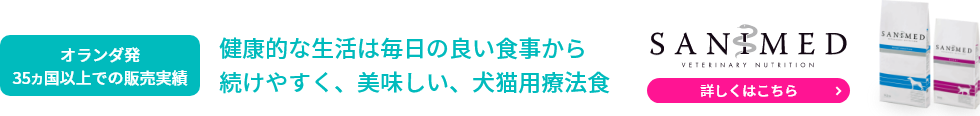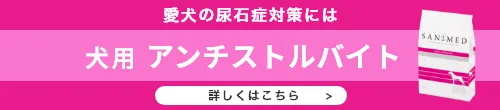猫の混合ワクチンは接種したほうがよい?接種スケジュールや費用などを解説

愛猫の健康を守るために考える必要がでてくることのひとつに「混合ワクチン」をどのように接種するか、ということが挙げられます。このワクチンは法律で義務付けられているわけではありませんが、猫同士で感染する可能性のある病気を防ぐために、接種が推奨されています。
今回のコラムでは、混合ワクチンとはなにか?なぜ接種したほうがよいのか?費用は?などといったことについて詳しくご説明しますので、お知りになりたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
猫の混合ワクチンは、どんな病気を防げるの?

まず、ワクチンとはウイルスや細菌といった病原体の毒性を弱めたりなくしたりしたものであり、こちらを接種することで体内に免疫をつくることができます。病原体が体内に入ってきたときにこの免疫が迎え撃つことで、病原体に感染しづらくなる、もしくは感染したとしても軽症で済むことが多く、感染症予防においてワクチンは非常に重要な役割を果たしています。
混合ワクチンは、複数の病原体に対する薬が1本の注射に含まれており、1回の注射で複数の病気を防ぐことが可能になります。「コアワクチン」「ノンコアワクチン」に大きく分けられ、該当する感染症は以下になります。伝染力が強いものもあり、感染した場合、特に幼猫が重症化するケースが多いです。
なお、これらのウイルスは人間には感染しません。
コアワクチン:生活環境に関わらず、すべての猫に接種すべきワクチン
① 猫 パルボウイルス (猫汎白血球減少症ウイルス) 感染症
感染猫の排泄物、嘔吐物などを介して感染します。非常に伝染力が高いウイルスで、ペットショップや多頭飼の場合など、あっという間に感染が広がってしまうこともあります。初期は元気消失や食欲不振が見られ、症状が進んでいくと、嘔吐や下痢などの消化器症状が見られます。また、その名のとおり白血球の減少や、それに伴う貧血が起こることもあります。
② 猫 ヘルペスウイルス 感染症
いわゆる「猫風邪」の原因のひとつで、猫ヘルペスウイルスI型による感染症です。大量の目ヤニや鼻水、結膜炎、くしゃみを連発する、発熱などが症状としてみられます。感染猫のくしゃみや鼻水が空気中に飛び散り、それを吸い込むことで感染します。症状が改善しても、身体内に潜んでおり、免疫力が弱まると再発してしまうことがあります。
③ 猫 カリシウイルス 感染症
猫ヘルペスウイルスと同様に「猫風邪」の原因となるウイルスです。猫ヘルペスウイルス感染症と非常に症状が酷似しており、併発していることも多く鑑別は難しいですが、舌粘膜の潰瘍による食欲不振が見られることがあります。
ノンコアワクチン:地域環境や暮らし方によって接種を検討すべきワクチン
① 猫 白血病ウイルス 感染症 (FeLV)
感染猫の唾液、尿などの接触や、食器の共有などでも感染するウイルスです。特に幼猫はウイルスに暴露された場合、感染、発症し死亡する確率が高くなります。感染した猫では初期には発熱、食欲不振など、また、免疫力が下がるため難治性の口内炎や下痢、時にはリンパ腫の発症が見られる場合もあります。
② 猫 クラミジアウイルス 感染症
猫ヘルペスウイルス、カリシウイルスと同様に「猫風邪」の原因となるウイルスです。主に結膜炎や鼻炎が症状として現れ、目ヤニや鼻汁に接触することで感染します。
③ 猫 免疫不全ウイルス 感染症 (FIV)
いわゆる「猫エイズ」です。感染しても発症しないケースもありますが、発症してしまった場合、免疫力が徐々に低下し、発熱や口内炎が見られたり、症状が進むと通常感染しないような病原体に感染したりすることで重症化、最終的にはエイズを発症し、免疫不全状態となり、死に至ります。主に感染猫に噛まれることで感染するケースが多いです。
日本で販売されているワクチンはコアワクチンを混合した3種混合ワクチンと、これに猫白血病ウイルスや猫クラミジアウイルスを加えたもの、さらにその他に猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルスの単独ワクチンなどが存在します。
日本で販売されているワクチンはコアワクチンを混合した3種混合ワクチンと、これに猫白血病ウイルスや猫クラミジアウイルスを加えたもの、さらにその他に猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルスの単独ワクチンなどが存在します。

*猫カリシウイルスは複数の型あり。
どの種類を接種すればよい?副反応はあるの?

どの種類のワクチンを接種すればよいか悩まれる場合もあるかもしれませんが、完全室内飼い、他の猫との接触の可能性がない場合はコアワクチンの「3種混合ワクチン」を接種、野良猫など他の猫との接触の可能性がある場合は、それ以上を検討、とするのがよいでしょう。
理由としては、コアワクチンで防げる感染症以外は感染猫との接触で起こるものであり、他の猫との接触がない場合は、接種の必要はないと考えられるからです。
前述したFIV、FeLVは血液検査で感染しているかわかる(ただし感染後1ヵ月は結果に反映されない)ため、特に保護猫を迎え入れる場合は、検査を検討してみてください。
いずれにしても動物病院によって方針や使用しているワクチンの種類は異なりますので、実際に愛猫にどの種類のワクチンを接種すべきか、まずは主治医の先生とご相談ください。
接種をするうえで気になるのが副反応ですが、起こる可能性は高くはないものの、あります。まず、例として接種部位の痒みや痛み、顔や全身が腫れる、元気消失・食欲不振が挙げられます。重篤なものとしてアナフィラキシーショックがありますが、こちらは接種後すぐ(30分以内)に起こることが多いため、しばらく待合室でなにも起きないか、待って確認することをお勧めします。
また、その後、仮になにかあっても対応ができるように、終日受診が可能な日の、午前中に接種するのがベストです。
さらに、猫ではワクチンを含めた注射の接種が原因で「注射部位肉腫」という、腫瘍を発症するケースがあることが知られています。そのため猫のワクチンは発症してもすぐ切除しやすい部位(後肢など)に接種されます。そのあたりにしこりができて、大きくなり、消えない場合は、可能性も考えられますので、動物病院を受診するようにしてください。
接種のスケジュールは?費用はどの程度かかる?

スケジュールについて、移行抗体(母体からの免疫)により守られている間は十分な免疫が得られない可能性が考慮され、1回目は生後8週 、その後1ヵ月あけて2回目接種、その後は1年ごとに追加接種、というのが現在日本では一般的になっています。
ただ、2024年にコアワクチンの接種頻度の国際的な方針が改定されているため、愛猫にとって最適なスケジュールについては、主治医の先生にご相談ください。
費用に関しては動物病院によって異なりますが、1回の接種につき5,000円~10,000円以内におさまるケースがほとんどです。
接種後に「ワクチン証明書」が交付されます。ペットホテルなどを利用する際に提示を求められることも多いので、なくさないようにしましょう。
まとめ

「うちの子は室内で暮らしているし、ワクチンは必要ないですよね?」というお声を聞くことがありますが、前述でも説明したとおり、ウイルスの中には環境中でも長い間生き残るものもあります。感染猫と私たち人間が接触し、服や靴などについたウイルスを自宅に持ち込んでしまう可能性もあるのです。
時には命もおびやかす感染症から大切な愛猫を守るために、主治医の先生と相談しながら、最適なワクチンを接種していくようにしましょう。